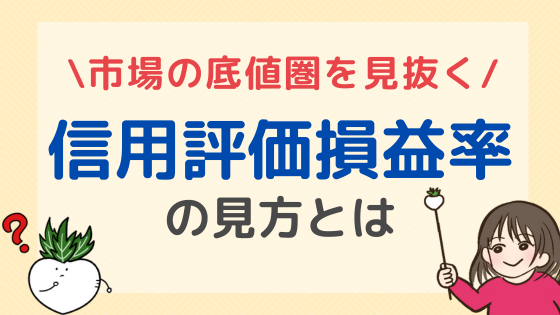
株式市場の変動に振り回され、投資に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな時、注目したいのが株式市場の底値圏・高値圏をはかるのに役立つ「信用評価損益率」という指標です。
この記事では、信用評価損益率の具体的な計算方法や、見方、投資判断に活かすためのポイントをわかりやすく解説していきます。
信用取引評価損益率とは
「信用取引評価損益率」とは、株の信用取引をしている人が、どれくらいの損をしているか、またはどれくらいの利益が出ているかを示すものです。
信用評価損益率の計算方法
信用評価損益率の計算方法は、証券会社によって異なりますが、おおまかに以下の方法で算出されています。
- 信用評価損益率(%)=評価損益額÷信用建玉残高(買い残のみ)×100
※信用評価損益率を確認できるおすすめのサイトは、記事のさいごで紹介しています。
評価損益
評価損益とは、今持っている株を売ったら、どれくらいの損益になるかを示すものです。まだ売却していないので、「含み損」や「含み益」とも呼ばれます。
買い残
買い残とは、証券会社からお金を借りて買った株のうち、まだ売っていない株のことです。

簡単に言うと、信用取引を使っている投資家の含み損益がどのくらいか?を表す指標!
信用評価損益率は通常マイナスになる
信用評価損益率を見る上で、重要なポイントがあります。それは、信用評価損益率が、通常マイナスになるということです。
なぜマイナスになるのでしょうか?一般的に、信用取引を利用する投資家は、利益が出た株はすぐに売って利益を確定させようとします。
しかし、損をしている株は、損失を確定させたくないため、なかなか売却に踏み切れない傾向があるのです。
そのため、信用取引では、含み損の状態になっている株が多く、信用評価損益率も、通常マイナス5%からマイナス20%程度の範囲で推移することが多いのです。
信用評価損益率で市場の過熱感をはかる方法
信用評価損益率がどのくらいの水準にあるかで、市場の過熱感がどの程度か、ある程度推測することができます。
| 信用評価損益率 | サイン |
| 0% | かなり買われ過ぎ |
| -5% | 買われ過ぎ |
| -20% | 売られ過ぎ |
| -40% | かなり売られ過ぎ |
信用評価損益の「買われ過ぎ」サインの特徴
信用評価損益率は、-5%を超えると買われすぎの目安となります。
信用評価損益率がほとんどの時期でマイナスあることから、信用取引をおこなう投資家の多くは、常に含み損を抱えているということになります。
しかし、株価が上昇し、含み損が減ってくると、状況は変わってきます。
信用評価損益率が0%に近づくと、多くの投資家が「そろそろ売ろう」と考え始めます。
これまで含み損を抱えていた投資家も、ようやく利益が出ると判断し、売り注文が出やすくなるのです。
このような背景から、信用評価損益率が0%に近づくと、売りが増加して、株価の上昇に歯止めをかけることから、市場が買われすぎの状態であることを示す目安となるのです。
しかし、信用評価損益率の「買われ過ぎサイン」は先行性が強いという特徴があります。
信用評価損益率が0%に近づいたからといって、必ずしもすぐに株価が下落するとは限りません。あくまで、将来的な株価の動きを予測するための参考となる指標です。
信用評価損益率の「売られ過ぎ」サインの特徴
信用評価損益率は-20%を下回ると売られすぎの目安になります。
過去のデータからも、信用評価損益率がマイナス20%を下回ると、株価が底打ちするケースが多いことがわかっています。
これは、「追証」が発生する水準に近づき、多くの投資家が損失を確定するために株を売却するためです。
追証とは、証券会社から借りているお金に対して、追加で保証金を払うことを指します。
信用評価損益率がマイナス20%を下回ると、多くの投資家が追証に追われ、やむを得ず保有している株を売却せざるを得ない状況に陥ります。
この大量の売りが一巡すると、売り圧力が弱まり、株価は底打ちし、反発する傾向があります。
さらに、株価が下落して割安になったと判断した投資家による新たな買いも加わり、株価は上昇に転じやすくなります。

信用評価損益率が-20%を下回ると、損切りのピークになりやすい!
ただし、信用評価損益率がマイナス20%を割ったからといって、必ずしも株価がすぐに反発するとは限りません。
過去には、リーマン・ショックやコロナ・ショックのように、信用評価損益率がマイナス40%を大きく下回る事態も発生しています。
特に、旧マザーズ市場のような新興市場では、信用評価損益率がマイナス48%まで下落するなど、極端なケースもみられる点には注意が必要です。
とはいえ、信用評価損益率がマイナス20%を割る水準で、割安な優良銘柄が増えるのは事実であり、株価の反発を期待できる目安となります。
さいごに
こまで、信用評価損益率の基本とその活用方法について紹介しました。
信用評価損益率は、株式市場の過熱感を把握するために役立つ指標のひとつです。特に、株価が暴落している時期には、信用評価損益率を知っておくことで、冷静な判断がしやすくなります。
また、普段信用取引を使わない人でも、信用評価損益率から信用取引の投げ売りピークを想定できれば、買いタイミングをはかるのに役立つのではないでしょうか♪
信用評価損益率が確認できるサイト
信用評価損益率は各証券会社のサイトで確認できますが、もっともおすすめなのは、「松井証券」です。※松井証券にログイン→投資情報→信用評価損益率を選択することで閲覧できます。
松井証券では、主に以下の情報が無料で見られるようになります。
- 当日の信用評価損益率
- 日経平均の信用評価損益率とその推移グラフ
- グロース銘柄の信用評価損益率と推移
一般的に、他の証券会社や新聞記事では、信用評価損益率を翌週に公表しています。
しかし、松井証券は、これに加えて松井証券で信用取引をおこなう投資家の信用評価損益率を毎日公表しているのでタイムリーな市場動向の把握ができます。
さらに、グロース市場に限定した信用評価損損益率が把握できます。中小型株に投資している個人投資家に特におすすめです!






